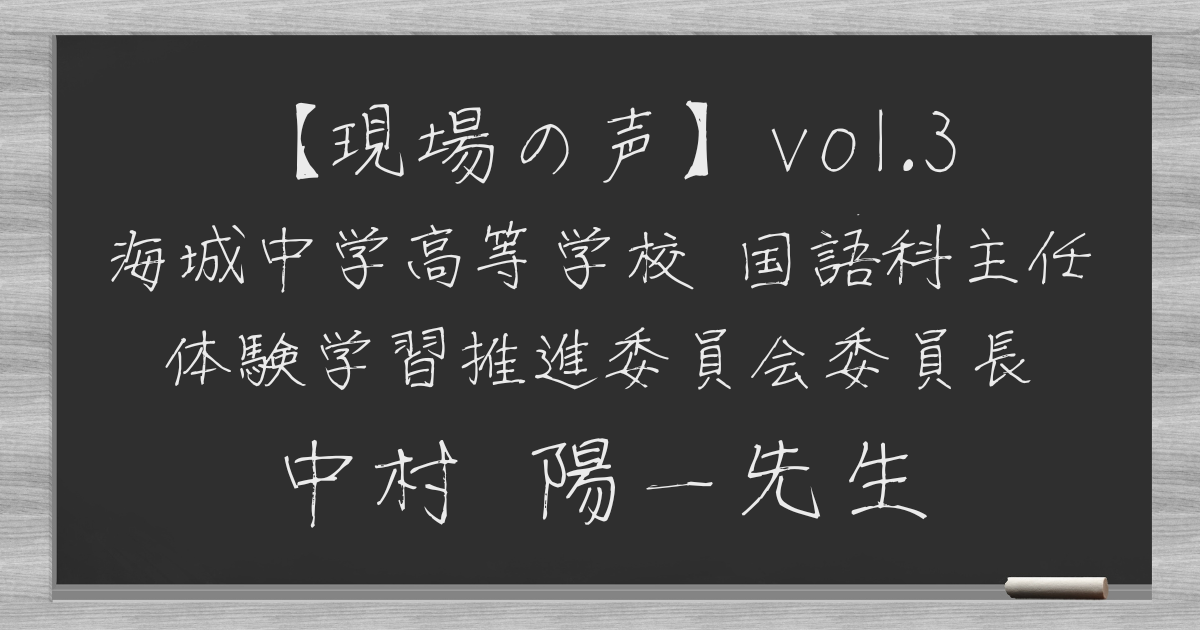【現場の声】では、実際にパブリックのワークショップを体験した学校や施設の方々から、ワークショップを導入したきっかけや、実施した感想や効果について、頂いたコメントをご紹介しています。
パブリックのワークショップに興味がある方や、これから導入を検討する方に参考にしていただければ幸いです。
中村 陽一先生からのコメント
「なぜ演劇ワークショップを学校現場に取り入れているのですか」
「価値観の異なる他者と協働し価値観の違いをいかしながら、新しい課題や決まった答えがない課題を創造的に解決する能力、前提を共有しない他者と対話するコミュニケーション能力、最後まであきらめずに問題に取り組む能力などなど、これからの時代に必要な能力の育成に適した活動だと考えるからです。演劇という営みはそのノウハウを宿命的に有していると考えています」
「すごい大きな話をしている気が……」
「がんばって理屈で説明するとこんな感じになります。理屈も大切です。でも、例えばPAVLICさんと実施するワークショップに楽しみながら夢中に取り組むうちに、子どもたちは大人が用意した理屈をこえて様々なことを主体的に学び取ります。楽しみながら学び合えることは演劇ワークショップの大きな魅力ですが、子どもたちは楽しく学び合いながら大人の想定を大きく超えていく」
「苦労されることはありますか」
「課題はまだまだありますね。より良い学びのために、どうしたら子どもたちが常にプレイフルでいられる場を創れるのかと悩むことばかりです。なので、PAVLICさんのような特別な方々と一緒にワークショップを創れることが大変ありがたい」
「いったいPAVLICの何が特別なのですか」
「簡潔に言えば演劇ワークショップに関する専門性の高さってことだと思うのですが、その中でも皆さんの持つ〈プレイフルな雰囲気〉が、生徒にとっても、教員にとっても本当に特別です。私もPAVLICのみなさんと一緒にワークショップをして、ふりかえりをする時間が本当に楽しい。教員が楽しんでいる雰囲気は生徒にも伝わります。その雰囲気は豊かな学びの場を創り上げると考えています。そんな説明で良いです?」
「すみません……あっ!」
「最後に『ん』がついちゃいましたね。今日はこれで終わりにしましょう。楽しかったです。これからも楽しく学び合えるワークショップをよろしくお願いします。ありがとうございました」
「助かりました。ありがとうございました」
ワークショップの様子
中高六年間のほとんどの学年において演劇的手法を活用したワークショップを実践している海城中学高等学校。
PAVLICは中学一年生を対象として年に三回、学校内外での生活において「お互いがほどほどに快適である」状態を主体的に作り出すことを体験的に学ぶ《カイテケーション(快適+コミュニケーション)・ワークショップ》を実施しています。
ワークショップは、プロの俳優たちによる短いお芝居を鑑賞することからスタート。
【通学時/休み時間/授業後の通学路】などのシチュエーションで起こりうるトラブルの事例を観たあと、生徒たちは「お互いがほどほどに快適」になり得るためにできることを考え、俳優たちが演じる登場人物たちに直接話を聞いたりアドバイスをしたりします。
そして後半は、シアターゲームやインプロ的な発表を実施。
今度は生徒たち自身が、トラブルが発生しそうな困難な状況の中で、実際に個人としてあるいは集団として、問題回避のために行動力を発揮できるかが試されます。
じゃんけんを通して、多くの人とコミュニケーションをとる

俳優が演じる”困りごとを抱えた人”と生徒たちが共演

担当講師より
 田野
田野海城中学校の一年生向けにデザインしたプログラムを「カイテケーション・ワークショップ」と呼ぶようになったのは2017年のこと。
長く定着して実施しているプログラムですが、コロナ禍なども経て毎年のように変容する生徒たちの個性や特徴に合わせ、先生方との綿密な事前打ち合わせと事後振り返りを欠かさずに行った上で、細かい微調整を加えながら常に新鮮に取り組んでいます。
中村先生、ワークショップを良く知る中村先生ならではの“遊び心”あるコメント、ありがとうございました!
中村 陽一先生、この度は素敵なコメントを
ありがとうございました。