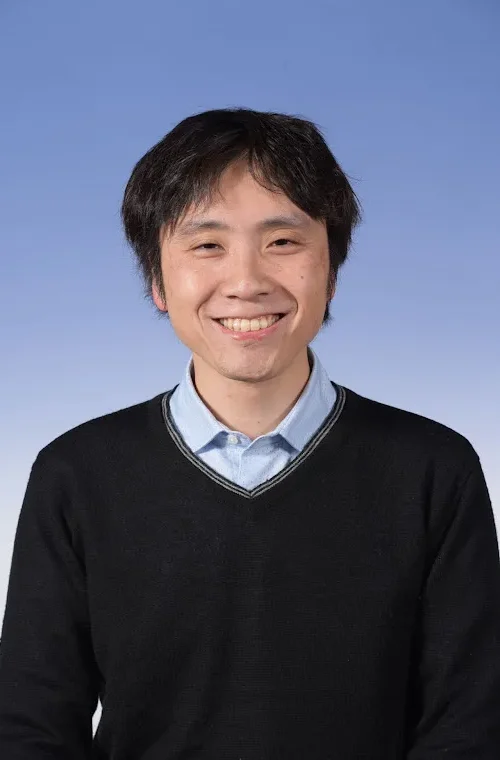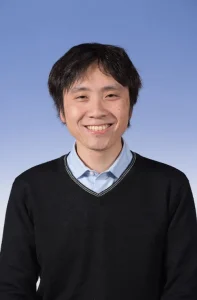【現場の声】では、実際にパブリックのワークショップを体験した学校や施設の方々から、ワークショップを導入したきっかけや、実施した感想や効果について、頂いたコメントをご紹介しています。
パブリックのワークショップに興味がある方や、これから導入を検討する方に参考にしていただければ幸いです。
森 大徳先生からのコメント
演劇には言葉と身体の両方を用いるという特性があり、創作の過程で、表情や身振り、動き、立ち位置など、さまざまな視点からアイデアを持ち寄ることができます。また、間や沈黙、身振り・手振りといった非言語的な要素について、その意味をともに見出したり深めたりすることも可能です。
こうした活動は、言語への関心の有無にかかわらず、生徒一人ひとりが自らの発想や持ち味を活かしながら、表現やコミュニケーションについて体感的に学ぶことを可能にします。
とはいえ、このような体験を日常の授業の中で実現するのは、教員ひとりの力では容易なことではありません。
PAVLICの皆さんは、ふだんの教室では得がたい、多層的かつ多面的な学びを実現するうえで、心強く、そして信頼のおける専門家集団です。
ワークショップ当日の様子
筑波大学附属駒場中・高等学校ではここ数年、森先生が担当している学年の学習過程に組み込む形で、年度ごとに実施プログラムを調整しています。
令和5~6年度は、生徒が創作した短歌をベースに演劇作品を創作するワークを実施しました。
講師陣によるデモ創作の発表

デモ創作で使用した短歌と上演されたシーンについて解説

担当講師より
 北村
北村生徒には、短歌と演劇という異なる表現手段を通じて、作り手・受け手という立場を交互に体験してもらいました。創作を通じて生まれるコミュニケーションや、作り手と受け手の間にあるコミュニケーションなど、森先生がおっしゃるように日本語表現とコミュニケーションについて多層的・多面的に体験し考察してもらうことがプログラムのねらいでした。
森 大徳先生、この度は素敵なコメントを
ありがとうございました。